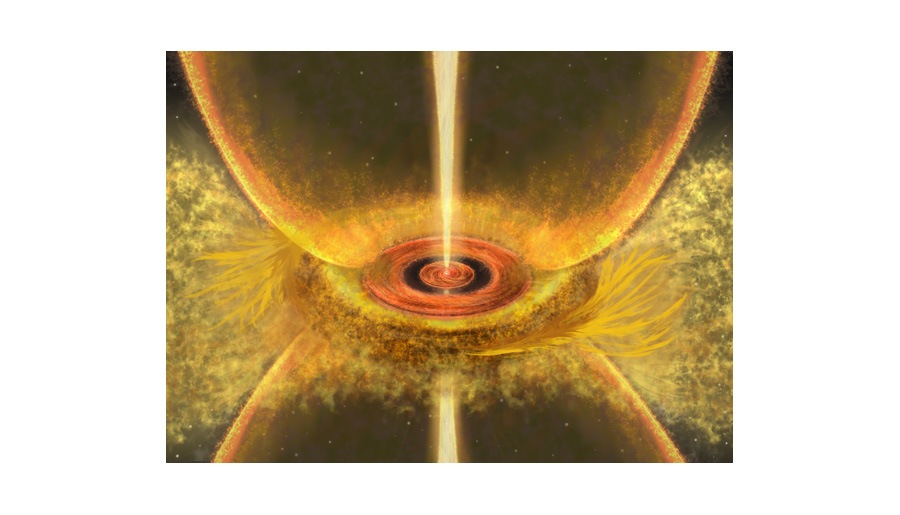九州大学、台湾中央研究院、工学院大学、国立天文台、足利大学の研究者からなるグループは、へびつかい座の星形成領域に存在する多数の若い星を観測したアルマ望遠鏡の公開データに対し、スパースモデリングと呼ばれる統計数理学を応用した超解像度画像解析手法を適用した解析を行いました。その結果、15個の円盤に未発見だった構造を発見しました。さらに、他のデータも組み合わせた統計解析により、星が誕生してから数十万年ほど経過すると、円盤に多様な構造が出現するという傾向を見出しました。
円盤に見られる多様な構造は、惑星の形成に伴って作られている可能性もあります。本研究は、惑星形成の過程を観測的、かつ統計的に解き明かす手がかりとなります。本学からは、武藤恭之教授(教育推進機構)が研究グループに参加しています。
この成果は、2025年4月22日に日本天文学会欧文研究報告誌に掲載されました。詳細は、以下の国立天文台のページをご参照ください。